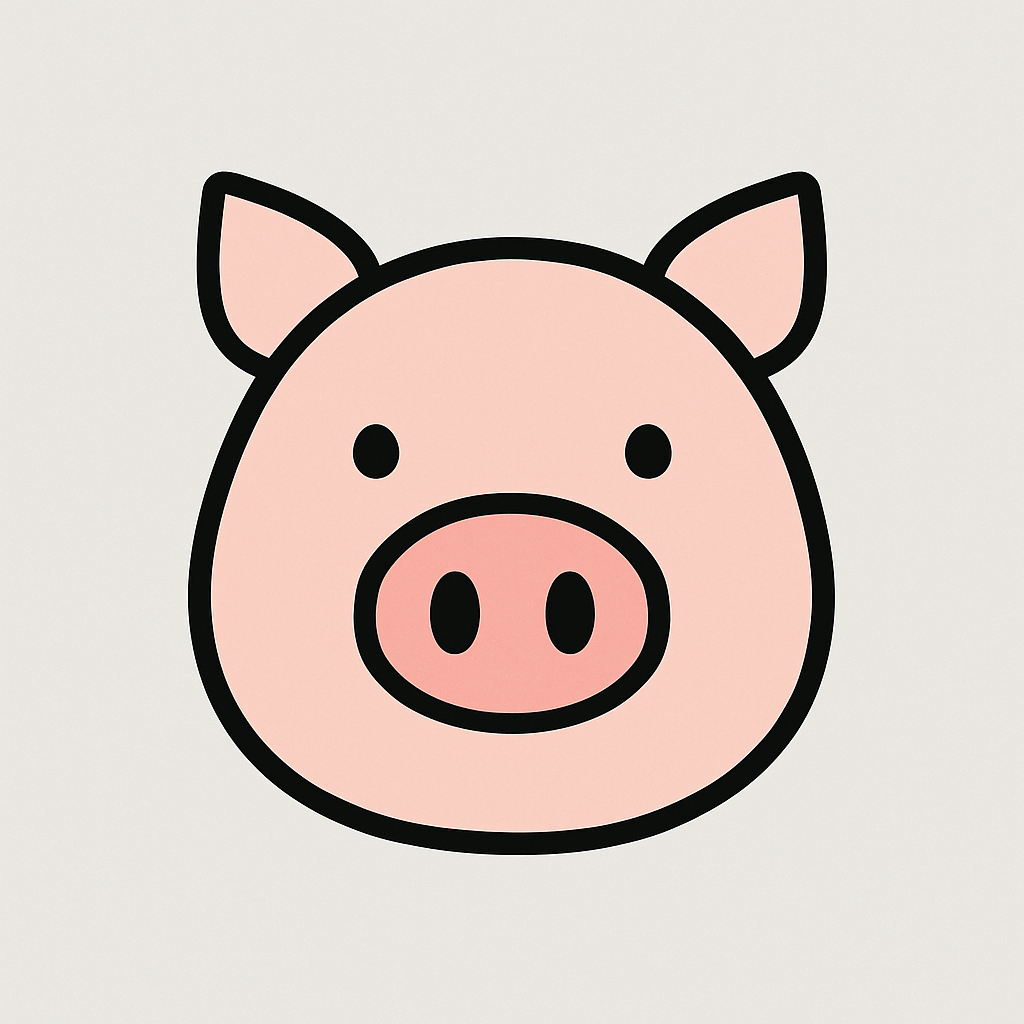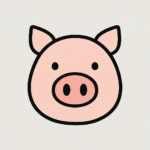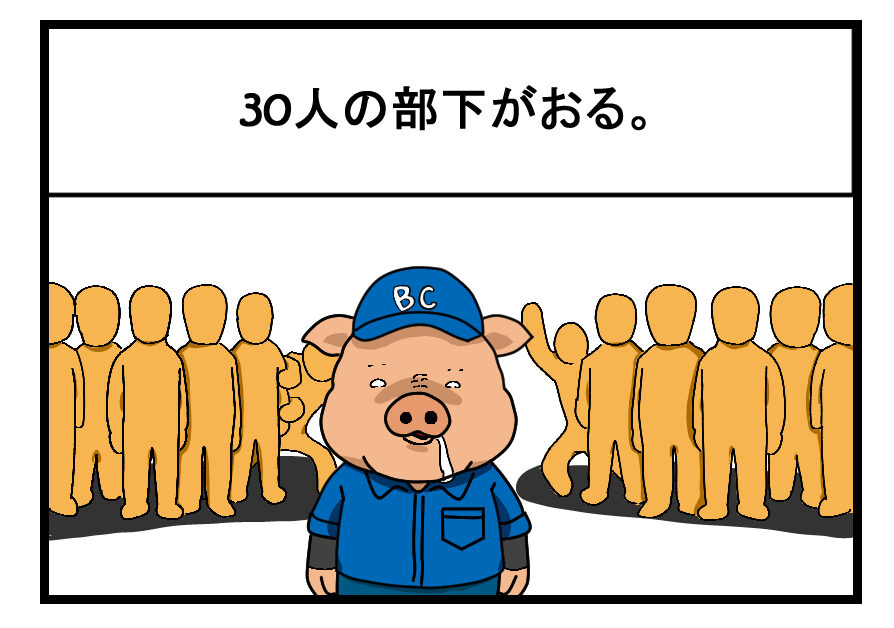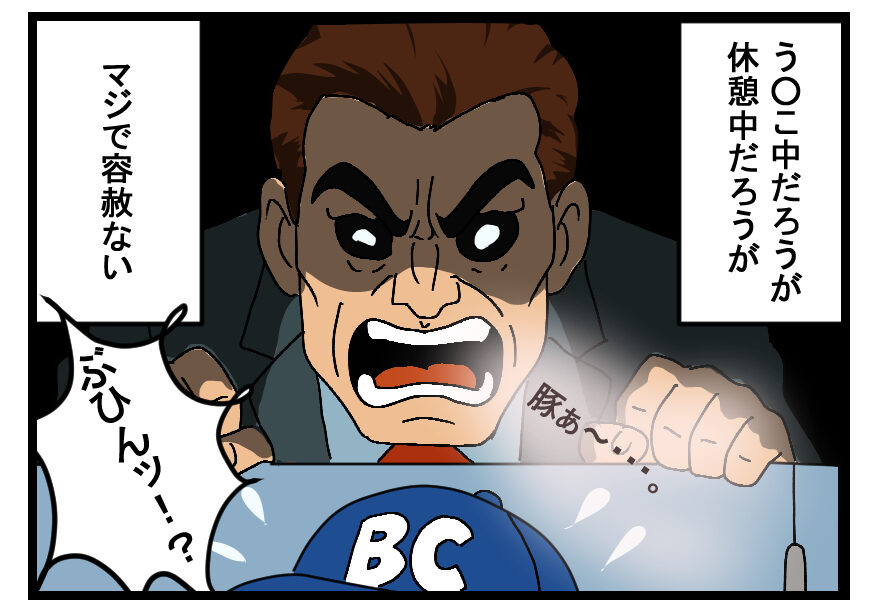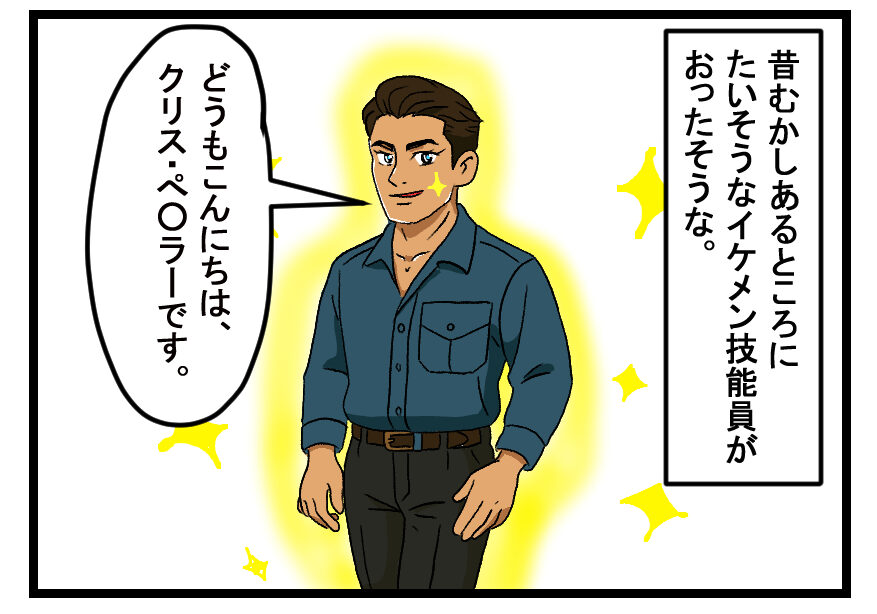お前の時間は・・・。

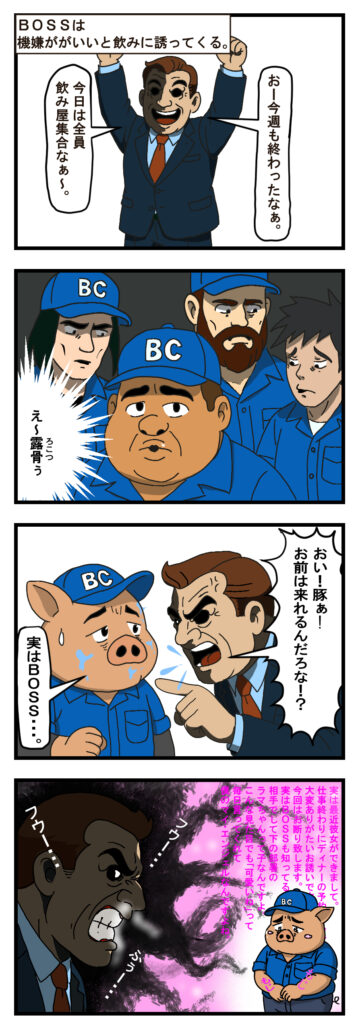
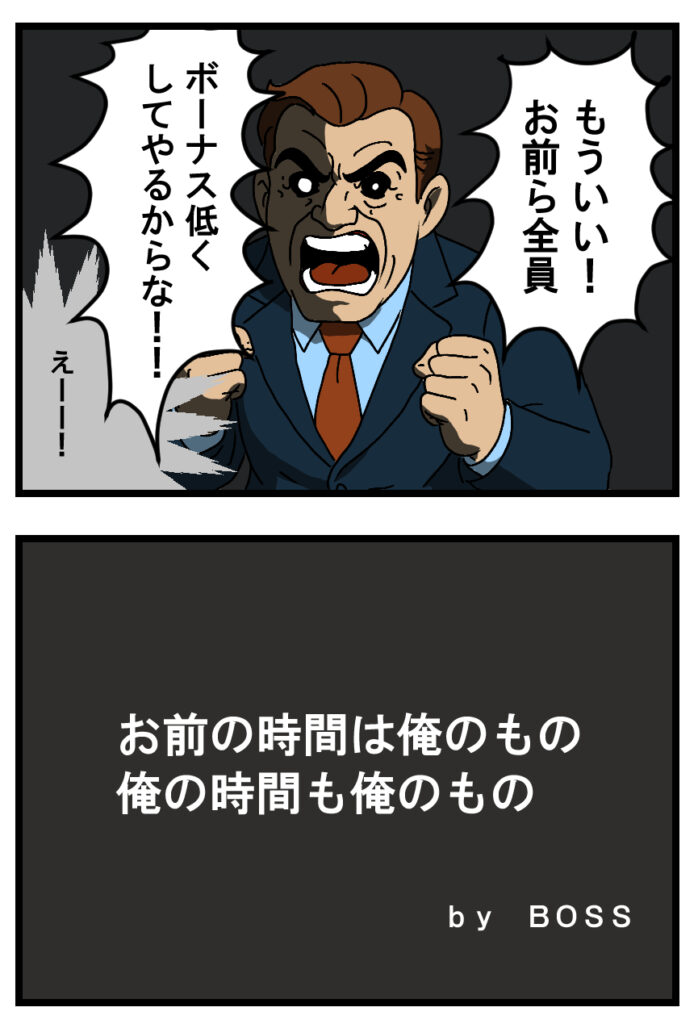
飲み会嫌い。
飲み会拒否はボーナス査定下げられる!?
■問題点は?
「飲み会に参加しない奴は協調性がない」
「空気を読まない社員にボーナスは出せない」
こんな言い分で、飲み会の欠席が人事評価に影響する職場は、ブラック企業にありがちな”昭和型ハラスメント体質”の典型です。
【主な問題点】
・プライベートの自由を侵害している。
・業務と無関係な私的行動で評価が左右される不当性。
・体質的な「同調圧力文化」の押しつけ。
・精神的苦痛や孤立感を招き、職場環境の悪化を引き起こす。
コンプライアンス的な問題は?
会社が「評価・処遇」に関して以下のような基準を設けている場合、社内コンプライアンスに抵触する恐れがあります。
●ハラスメントの一種とみなされる場合も
・「飲み会強制」や「参加しない社員への不利益扱い」
⇨パワハラ(職場の優越的地位を利用した不当な扱い)と判断されることがあります。
●公平・公正な人事制度の欠如
・業務上の成果や勤務態度とは関係ない行為でボーナス査定を下げる。
⇨評価制度の公正性を損なう=内部統制・論理違反にあたる可能性
労働基準法との関係は?
労働基準法では、明確に「飲み会と評価」の関係を定めている条文はありません。
しかし、以下の観点で問題となり得ます。
●労働契約法 第3条・第5条
・合理的な評価基準が必要(第3条:信義則・公平性)
・安全配慮義務違反(第5条):不公平な評価がストレスやうつ状態を招いた場合、会社の責任が問われる可能性あり
●就業規則違反や賃金規程の逸脱
・評価の根拠が曖昧で、恣意的に査定が下げられた場合、労基署や裁判で争われる事例も実際に存在します。
まとめ
問題点
⇒飲み会の有無でボーナス査定を下げるのは不当・不合理
コンプライアンス
⇒ハラスメント・不公正な人事評価の可能性あり
労働基準法
⇒安全配慮義務・合理性原則違反の可能性あり
本質
⇒飲み会は仕事ではない。評価基準にすべきではない。
「飲み二ケーションが大事」は、もはや時代錯誤。
ボーナスは「飲みの回数」ではなく「働きの中身」で決まるべきです。